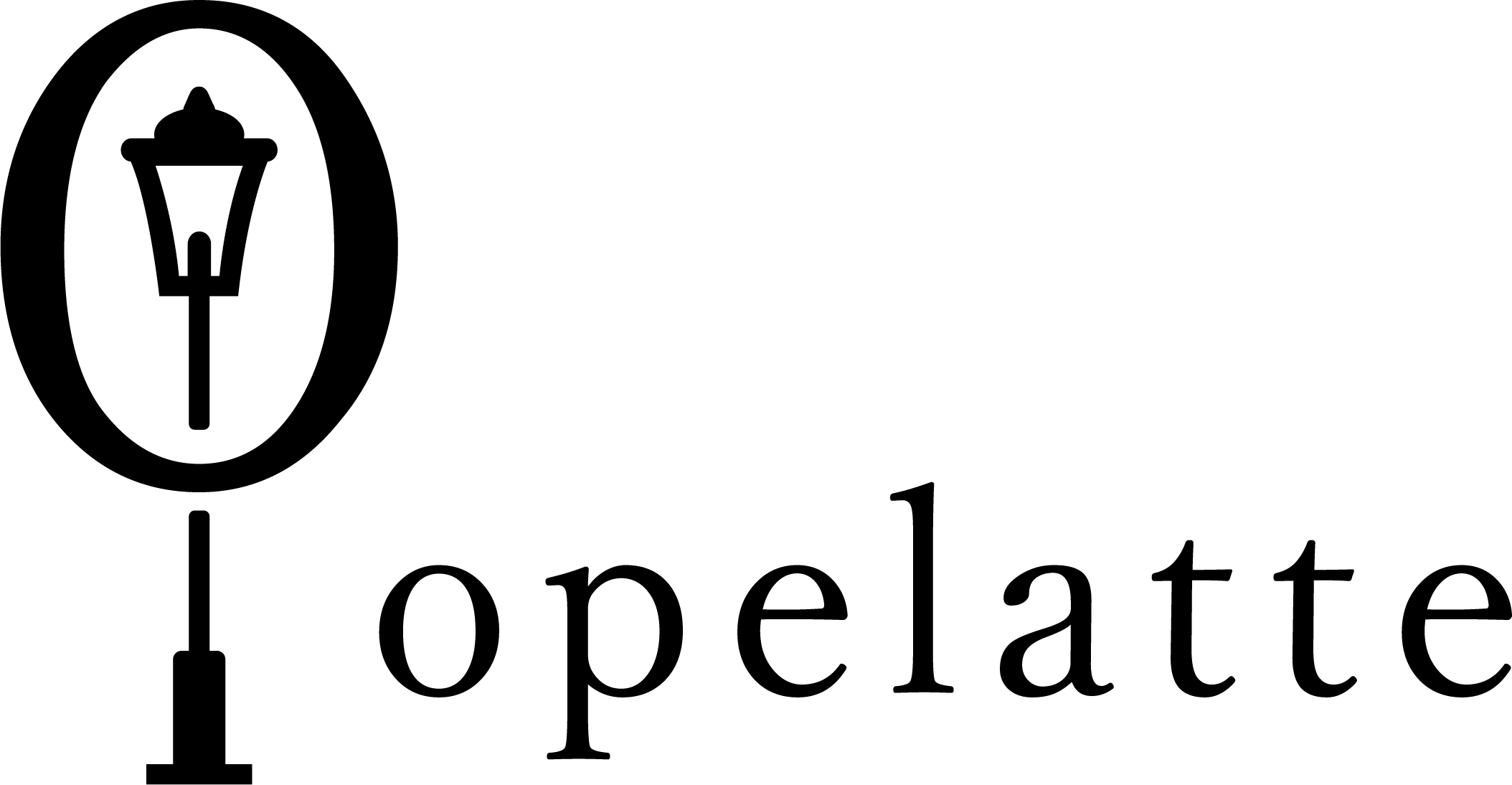コロナ禍のフードロス
~和菓子屋の挑戦~
需要の減退を乗り越え、店舗存続へ
新型コロナウイルスの感染拡大は、私たちの生活に大きな影響を与えました。特に飲食業界は、外出自粛や営業時間短縮などにより、深刻な打撃を受けました。和菓子屋も例外ではなく、多くの店舗が客足の減少に悩まされました。
今回は、コロナ禍で需要が減退し、フードロスに直面した和菓子屋E社が、どのように課題を克服し、店舗の存続を果たしたのか、その取り組みをご紹介します。
コロナ禍でのフードロス発生
E社は、創業以来、地域に根ざした和菓子屋として、地元住民に愛されてきました。しかし、コロナ禍で人の流れが止まり、観光客だけでなく、地元住民の来店も減少。E社は、これまで経験したことのないほどの需要減退に直面しました。
和菓子は、生菓子を中心に日持ちがしないものが多く、売れ残りは廃棄せざるを得ません。E社では、毎日心を痛めながら、大量の和菓子を廃棄処分していました。廃棄される和菓子は、食材の無駄遣いであると同時に、製造にかかったコストも無駄になり、E社の経営を圧迫しました。そこから株式会社opelatte(オペラテ)との協業が始まりました。
地元宿泊施設・商業施設との提携
この状況を打破するため、E社は新たな販路開拓に乗り出しました。まず、地元の宿泊施設に和菓子を客室のお茶菓子として提供することを提案しました。宿泊施設側も、コロナ禍で客室稼働率が低下しており、新たなサービスで集客を図りたいと考えていました。E社の高品質な和菓子は、宿泊客に喜ばれ、施設の評判向上にも貢献しました。
さらに、E社は地元の商業施設にも販路を拡大しました。商業施設内のイベントスペースで、和菓子の販売会や実演販売を実施。施設を訪れる人々に、E社の和菓子の魅力を直接アピールしました。
これらの取り組みは、E社にとって大きな転換期となりました。これまで、店舗販売に頼っていたE社が、新たな販路を開拓することで、コロナ禍でも安定した売上を確保できるようになったのです。
認知度向上とEC販路拡大
新たな販路開拓と並行して、E社は認知度向上にも力を入れました。地元の新聞やテレビなどのメディアに積極的に取り上げてもらうことで、E社の存在を広く知ってもらうことに成功しました。また、SNSを活用した情報発信も強化し、若い世代へのアプローチも積極的に行いました。
さらに、E社はECサイトを立ち上げ、オンライン販売を開始しました。これにより、店舗まで足を運ぶことが難しい遠方のお客様にも、E社の和菓子を届けることができるようになりました。ECサイトでは、季節限定の商品や、オンライン限定のセット商品などを販売し、顧客のニーズに応えています。
コロナ禍という逆境において、E社はフードロス削減と経営安定化を両立させました。地元との連携、積極的な情報発信、EC販路拡大など、様々な取り組みが功を奏した結果と言えるでしょう。E社の事例は、コロナ禍で苦境に立たされている他の和菓子屋にとっても、希望となるのではないでしょうか。
E社の取り組みから得られる教訓
- 販路の多様化は、経営安定化に不可欠である。
- 地域との連携は、新たな可能性を生み出す。
- 情報発信は、顧客とのつながりを強化する。
- ECサイトは、販路拡大の有効な手段となる。
コロナ禍は、多くの企業にとって大きな試練となりました。しかし、E社のように、変化を恐れず、積極的に行動することで、危機を乗り越え、新たな成長を遂げることができるのです。